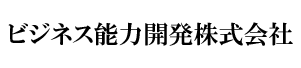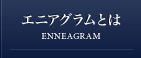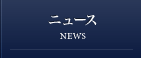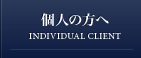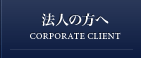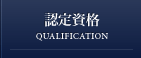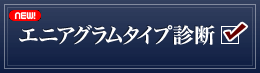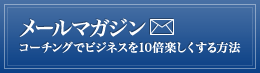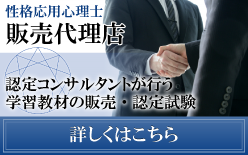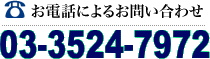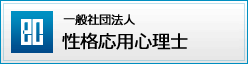2022/10/04
【メーシー教授】自己認識_2
前回、自己認識能力の低い人は、自分が高い能力を持っていると誤解しがちと学びました。そのような部下を改善するには、理解不足がわかる客観的な証拠を出して、部下に気づきを促しつつ、仕事力の向上を図ることがポイントとのこと。どういうことでしょうか?性格応用心理学(エニアグラムコーチング®)専門家のメーシー教授が答えます。
■人物紹介
 メーシー教授
メーシー教授
秋田県出身。専門は性格応用心理学(エニアグラムコーチング®)。ビジネスにも詳しい。
 さくらちゃん
さくらちゃん
大学3年生、心理学専攻、テニスサークル所属。趣味は食べ歩き。特にケーキには目が無い。
 (さくらちゃんの)パパ
(さくらちゃんの)パパ
人事系コンサルタント会社経営 メーシー教授からビジネス上の課題にアドバイスをもらっている。

メーシー教授、今日も宜しくお願いします。
前回、自己認識能力の低い人は、自分が高い能力を持っていると誤解しがちと伺いました。
さらに改善方法が伺えればと思います。

上司がいくら口頭で注意したりアドバイスしたりしても、デキないのに自信満々の部下の心には響かず、行動が改善されない、ということがままある。

そのような部下には本当に困ります。

能力の低い人は何かをする能力がただ低いというだけでなく、自分の能力が低いことに気づく能力も低いということ。
まさにこのことが、なぜか仕事のデキない人ほど自信を持っていることの理由と言える。

困った自信です。

そんな場合は理解不足がわかる客観的な証拠を出して、部下に気づきを促しつつ、仕事力の向上を図ることがポイント。

と、言われますと・・・。

部下が「分かった」と言っても、内容を説明させれば良い。
本当に分かったのでなければ、説明は出来ない。

なるほど、確かにそうですね。

さらに、「出来る」というのならば、出来ている人を10点として、自分は何点か自己採点させる。

それでうまくいきますか?

仮に自己採点を8点とした時、10点の人と合致している8点の項目と内容を自分の言葉で説明させる。

そこまでやれば気がつきますね。

「自己採点」というところがポイント。
人から言われるのと違って、自己採点となれば、結果を客観的事実として受け止めざるを得ない。

なるほど。やはり自分を客観的に見、「己を知る」ということが重要なのですね。
今日も良いことを教えて頂き勉強になりました。
有難うございました。